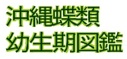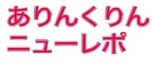◆ありんくりんニュース
★「ありんくりん通信 5号」の発行を終え
---------------
「ありんくりん通信 5号」(双尾II、2015年7月15日発行)
-------------- |
 |
波照間島のヤエヤマカラスアゲハについて、新田智は、本種の食草であるハマセンダン・カラスザンショウが自生していない事から、同島での本種は迷蝶ではないかと思い、渡島するたびに注意してました。移動蝶と感じていたことから、前翅の翅先の鱗粉を指でとりマーキング、飛んでいて遠くから見ても同じ個体をカウントしないようにしています。マーキングをして行く中で、翅型や尾状突起の形状など明らかに八重山産とは違うと感じた個体を採集、これらの標本をカラスアゲハの研究家である相澤和男氏に写真判定してもらいました。※掲載標本写真はこちら。
ここに詳しい解説をしていますが、本誌に掲載の写真は「台湾型」、「台湾または台湾緑島型」、「台湾緑島または中国本土型」図示ししました。また、比較用に「八重山型」も図示しましたが、この型でも変異が多い事が分かります。特に、西表島の「八重山型」個体は、後翅の青が美しくのっています。
*************
★改めてここに、相澤和男氏のコメントを書き留めておきます。
1.前翅;外縁が内側に入り込むのは緑島産だけで、台湾産、八重山産は真直ぐになります。
2.尾状突起;緑島産は長く途中窪みがあります。台湾産はもっと太いですし、八重山産は基本的に短くズンドウです。
3.前翅裏面;台湾産は基本的に黒いです。
重要な点は翅型と尾状突起の形状、地色なのですね(このことはカワカミシロチョウとナミエシロチョウなどの区別点にも通じます)。
*************
それから、本部町水納島の個体は、中国大陸からのヤエヤマカラスアゲハということで、大変興味深いです。新田智はこの記録に関しましても、当時は台湾型と報告(「新田智 沖縄県本部町水納島の蝶、蝶研フィールド114(1995).」)していた事に少し疑問を残していたようで、相澤氏の再鑑定のおかげで「中国本土型、P.
bianor bianor(記載名義亜種)」で決着がつき訂正できて良かったと感じているようです。
※沖縄離島の記録分布表で、この記録(蝶研フィールド114)を取り上げオキナワカラスアゲハにプロットされたケースがあるので、これは明らかな間違いでヤエヤマカラスアゲハにすべきと思っています(そうなると本部町水納島のオキナワカラスアゲハは未記録?、正式な記録をご存知の方はご教示頂けるとありがたいです)。
さて、波照間島でのマーキング個体に関して、その後さまざまな問題が生じました。私(新田敦子)は誌面・記録に残す事は重要かとは思いますが、発生の根拠や科学的な追跡調査などを行わない先走った記録に関して、他者から訂正や根拠を求められた時に、科学的に証明できず、明らかな間違いであったと感じたら、報告者ご自身が潔く記録の取り下げをすべきではないかと思っています。真偽を知る一人として、その後の混乱が大きくなってしまった事を非常に残念に思っています。すでに時効になったと感じたのでここに書き留めておきます。
-----------------
「沖縄蝶の食草」というコーナーでは食草(植物)が主役です。今回はシュロガヤツリです。セセリは巣を作るので探すのが簡単です。
------------------------
巻末の「琉大風樹館コレクション」は「沖縄島のマルバネルリマダラ♀」ラベルには「N.Park Okinawa Is. 1-VIII-1967
M.Zakimi」(沖縄県(沖縄島)N.Parkは(名護公園らしい) 1967年8月1日 M.Zakimi)とあります。恐らく未発表?※掲載標本写真はこちら。
『ありんくりん通信5』記録覚書
●蝶の食草;シュロガヤツリ;チャバネセセリ、イチモンジセセリ(新田智・新田敦子 蝶の食草 シュロガヤツリ、ありんくりん通信5、5)
|